パナソニックグループ
対談:取締役会議長 澤田道隆氏 × 社外取締役 重富隆介氏 グループ経営改革を支える取締役会の姿
2025年09月24日
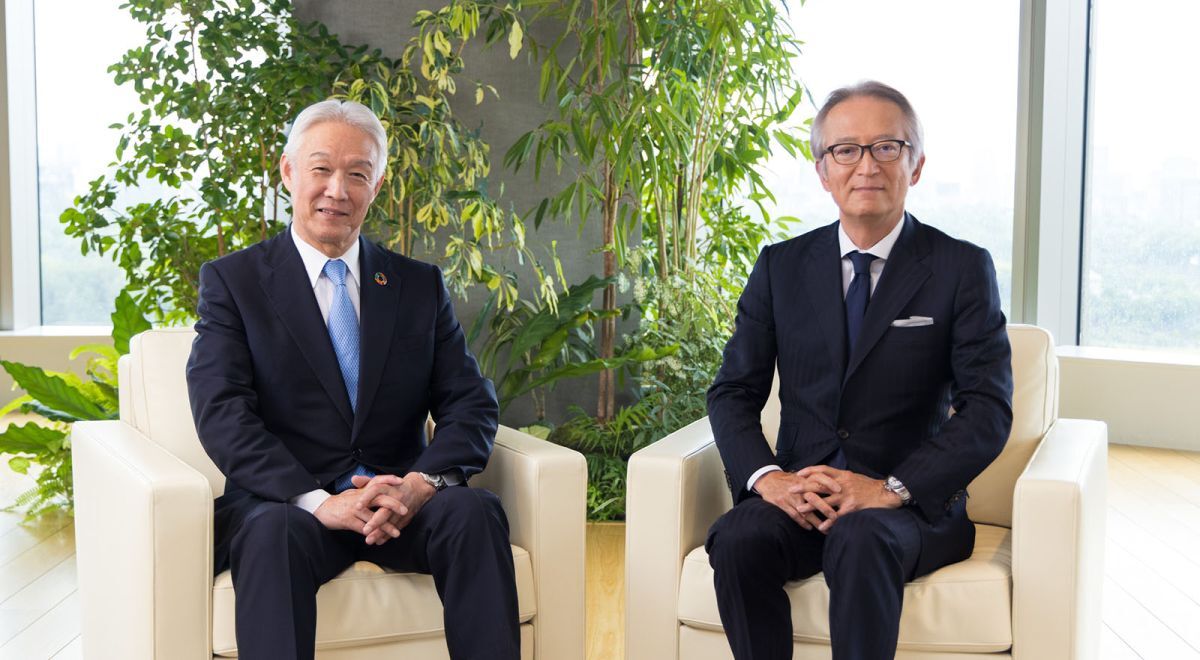
2025年、パナソニックグループは「黒字の中での改革」という前例のない挑戦に踏み切った。企業価値の長期低迷に終止符を打ち、資本市場の信頼を回復するため、取締役会はかつてないスピードと覚悟で議論を重ねている。本対談では、社外取締役であり取締役会議長を務める澤田 道隆氏と、2024年6月に社外取締役に就任した重富 隆介氏が、グループ経営改革の舞台裏、取締役会の構造変化、そして「パナソニックグループは何の会社になるのか?」という問いに向き合う。社員との協働、ソリューション領域での戦略、そしてキャピタルアロケーションの本質的な議論――。未来のパナソニックグループを形づくる「覚悟」と「構想」に迫る。
オリジナル記事:パナソニックグループ統合報告書 2025より一部編集して掲載しています。全文はパナソニックグループ統合報告書 2025よりご覧ください。
過去とは異なるスピード感で議論。目標必達が最重要
――今回、黒字の中でグループ経営改革を実施することや、改革の内容について、取締役会ではどのような議論をされたのでしょうか。また、今回のグループ経営改革で最も成し遂げたいことは何でしょうか。
澤田:2024年度は売上・利益共に公表値を上回り、非連結となったオートモーティブを除き、全てのセグメントで営業利益が増益となりました。しかしながら、取締役会では、黒字であってもこのままでは大きな成長は見込めない、株主の期待には応えられていないとの危機感があり、グループ経営改革の議論を開始しました。その議論の主な内容は、重過ぎる固定費構造にメスを入れ収益改善を進めることに加え、今後どのような事業に集中しなければならないかを明確にする、すなわち事業ポートフォリオマネジメントを加速させることです。今回のグループ経営改革で最も成し遂げたいことは、固定費構造改革・事業ポートフォリオマネジメントの加速といった宣言したことを必達し、株主の期待に応えることです。2026年度に1,500億円以上の収益改善などの目標が達成できれば、資本市場からの信頼回復につながると考えています。

パナソニック ホールディングス株式会社 社外取締役・取締役会議長
澤田 道隆(さわだ みちたか)氏
重富:私自身は2024年6月24日に社外取締役に就任し、実質的には7月からさまざまな議論に参画してきました。パナソニックグループの将来像を描くことについては、取締役会がスピード感を持って議論することが重要だと考えていました。当初は取締役会で6カ月から1年ぐらいかけて、グループ経営改革について議論する予定でしたが、3カ月という短期間の中で結論を出すことの重要性が取締役会での共通認識となり、それが2025年2月4日のグループ経営改革プランの発表につながりました。当社の企業価値の長期低迷については、執行側も監督側も強い問題意識を持っており、待ったなしの議論となりました。私も約束したことを成し遂げることが最も重要と認識しており、取締役会でしっかりと進捗を監督していきます。
経営改革の議論の解像度が増すにつれ、事業会社の危機意識が向上
――取締役会でグループ経営改革を議論する中で、楠見グループCEOを中心とする執行側の覚悟や危機意識の変化など、社外取締役として感じていたことがあれば、教えてください。
重富:時間軸に対する考え方は以前の当社からは完全に変わりました。先ほどの話の通り、今回のグループ経営改革についても、当初は6カ月から1年かけて議論する話でしたが、3カ月で結論を出すことになりました。楠見グループCEOのリーダーシップの下で、スピード感を持ってしっかりとまとめ上げたものであり、過去との大きな違いであると感じています。また、株価や時価総額を意識した議論が取締役会で常に出てくるようになりました。資本市場の声にしっかりと耳を傾け、エンゲージメントしながら、当社として何をやるべきなのか判断する姿勢が強化されています。

パナソニック ホールディングス株式会社 社外取締役
重富 隆介(しげとみ りゅうすけ)氏
澤田:楠見グループCEOの危機意識はもちろん高いわけですが、執行の中でも事業会社レイヤーではその危機意識にバラつきや温度差があると感じていました。そのような中で、取締役会で真剣かつ真摯な議論が進むにつれて、執行内での危機意識や覚悟が一気に高まりました。その背景としては、固定費構造改革には相当の痛みが伴い、パナソニックグループがどのような企業として生き残るのかを明確にする中では、撤退する事業も出てきますので、自分事として差し迫ってきたのではないかと捉えています。これまでの当社の時間軸では2月4日のグループ経営改革の発表は実現できていなかったと思います。今回、加速するように議論が進みましたが、現在はまだスタート地点に立った状態であり、ここからが本当の勝負です。
執行側の事情に影響されない取締役会の運営
――社外取締役の取締役会議長への就任は、当社では初めてのことです。その意義をどのようにお考えですか。
澤田:監督と執行の分離によるガバナンス強化という観点では、社外取締役が取締役会議長を担う意義は大いにあると考えています。私自身も花王株式会社の社長時代、2014年から社外取締役に取締役会議長を担っていただきました。その経験から言うと、議長が執行側の内部の事情を深く知っていることはプラスに働く場合もありますが、マイナスに働く場合もあるように思います。例えば、自社の常識が世間の常識とずれていても、あまり気にせずに議論を進めてしまい、貴重な意見が出てきても重く捉えないことがあり得ます。また、執行側での阿吽の呼吸が取締役会での説明の省略につながり、社外取締役が発言しにくくなることも考えられます。もちろん社内の状況を十分に知らないが故に、取締役会を上手く運営できない面もあるかと思いますが、当社は大きな変革期にあるので、社外の視点でガバナンスを強化させることを考えると、これまでとは異なる新しい体制で臨む意味があると感じています。
重富:社外取締役が取締役会議長に就任する一番の利点は、社内の事情や慣習といった制約要因にとらわれずに、取締役会の議事を進行できることです。ただし、単に社外取締役が議長になればよいということではありません。澤田さんのように大企業での経営経験があり、どのようなさじ加減で議論を進めればよいのか分かっている方でなければ務まりません。だからこそ、今回、澤田さんに就任いただいた意義は大きいと考えています。また、取締役会事務局には澤田さんと本音でぶつかってもらいたいと思います。私も大企業にいたのでよく分かりますが、どうしても取締役会議長や社長の顔色を見ながら、議案の上程の仕方などを考えてしまいます。せっかく澤田さんのような方に議長に就任いただいたので、事務局も遠慮せずに対応し、取締役会での有意な議論につなげていただくことが肝要です。
定期的なモニタリングと期限を明確にした対応が必要
――大型投資案件である車載電池とBlue Yonder社に対して、今後の取締役会ではどのように監督し、仮に想定通りのリターンが望めなくなった場合、社外取締役としてどのように対応するお考えですか。
重富:当社の将来を考える上で、車載電池とBlue Yonder社は非常に重要な事業です。経営状況、運営状況について、しっかりとモニタリングする必要があります。その上で、必要に応じて戦略的な選択肢を執行側から提示してもらうほか、取締役会でしっかりとしたメニュー作りまで行う選択もあると考えています。例えば、Blue Yonder社については、ソフトウェア業界では成功したロールモデルがないと、飛躍的な事業成長につながらない面があるので、成功事例を早く作ることが重要です。また、経営が想定通りに進まない可能性も考える必要があります。最も良くないことは、業績が悪化しているにもかかわらず、その状況を放置することです。業績悪化の原因を分析し、それに対するオプションメニューの設定をすぐに行い、期限をしっかりと決めて、それまでに判断していく必要があります。期限については、起点をどこにするのかということはありますが、24カ月よりも長く取ることは基本的にはないと考えています。12カ月から18カ月の間で期限を設定し、事前に決めたKPIや通過点としてのマイルストーンが達成されているかどうかを検証する必要があると認識しています。
澤田:車載電池やBlue Yonder社への大型投資を決めた背景には、当社の経営の在り方を変えなければならない、新しいモデルを作るという観点もあったと認識しています。車載電池は大きな市場変動がある中で、アクセル・ブレーキをどのように踏むのかといった迅速かつ研ぎ澄まされた経営判断が必要です。Blue Yonder社はソリューションを中心としたソフトウェア型ビジネスを担う経営能力が必要です。取締役会としては、当初の予定通り進んでいるかどうかモニタリングするとともに、軌道修正が必要な場合は迅速に執行側に要請していきます。また、これらの大型投資が経営の在り方の変革につながっているのかという点も、併せてチェックしていきます。
成功のカギは、ソリューション領域での戦略
――「パナソニックグループは何の会社になるのか?」と、資本市場から長年にわたり、問い続けられています。取締役会議長として、取締役会でこの問いにどのように向き合い、答えを出していくお考えですか。
澤田:当社の現状を踏まえて正面から答えると、「デバイス領域、スマートライフ領域を高収益化しながら、ソリューション領域で利益を生み出し成長する会社になる」ということだと思います。資本市場から見えていないのは、ソリューション領域での利益の創出と成長の実現をどのように成し遂げるのかという点だと認識しています。小さな事例でも良いので、成功事例を積み上げていくことが大事です。また、これまで当社は真正面から戦ってきました。そのため競争が激しくなると採算が悪化し、撤退を余儀なくされることもありました。これまでは戦う戦略を選択してきたわけですが、この構図を変える必要があると感じています。「戦略」とは、字のごとく「戦い」を「略する」、つまり、できるだけ戦わずに勝つのが戦略の本質であると考えています。戦わずに勝つためには、視点を変える、先行する、スピーディーに取り組む、格段に高い技術で臨むなどの差別化が必要です。ソリューション領域で勝つには、このようなことが必要なのではないでしょうか。成功事例を複数持つことができれば、ソリューション領域の成長と利益の拡大につながります。その結果、企業価値が向上し、資本市場の皆様の期待に応えられると考えています。
重富:当社には世界に冠たる技術が多々ありますが、それらが利益を伴った事業展開に結び付いているかどうかは疑問があります。澤田さんのご指摘の通り、私もレッドオーシャンの競争が激しい市場で戦うビジネスの形で本当に良いのかと感じています。プレイヤーの数が限られているにもかかわらず、相応の市場規模があるビジネスは世の中にいくらでもあります。そのような市場にリソースを集中させて勝負する方が、リスクを抑えつつリターンを拡大させることができます。これはまさに取締役会で議論している事業ポートフォリオの再構築や、キャピタル、リソースのアロケーションの話であり、取締役会で議論すべき本質的なテーマです。当社は潤沢にキャッシュを生み出す事業が何で、どの事業あるいは事業分野にそのキャッシュとリソースを配分すれば、5年後10年後の収益力が最大になるのかを考える必要があります。過去のしがらみや会社の伝統などに縛られずに、事業を再構築する時が来ています。これらをやり切れれば、パナソニックグループが再度日本のリーディングカンパニーとして、かつ、世界に冠たるブランドになれると考えています。
過去にないレベルでのキャピタルアロケーションの議論が必要
――当社に対しての課題認識や何かお感じになることはありますか。
澤田:パナソニックグループは優秀な人たちの集まりですが、議論が一定程度まで進むと、意見を徹底的に戦わせ、議論をし尽くすというよりも、きれいに整理し、取りまとめてしまう傾向があると感じています。結果的に、成長に結び付かないまとめ方をしているケースが多いです。スタッフの皆さんのまとめ方には納得性はある一方で、ワクワク感がないと感じています。今後はある種の貪欲さや、自分たちの夢を信じて突き進む部分がより必要と考えています。
重富:本当の意味でのキャピタルアロケーションやリソースアロケーションについて、取締役会で踏み込んだ議論がされていないと感じています。例えば、キャピタルアロケーションについては、今後6カ月あるいは12カ月で出てくる具体的なキャピタルの金額を、どのように配分するのかという議論を今までしていなかったと認識しています。グループ経営改革を発表した以上は、それを最も効率的に達成するために、取締役会のテーブルの上に具体的な事業を並べてキャピタルアロケーションの議論をする必要があります。この議論を取締役会ですることで、投下した資本へのリターンが明確になり、当社がより強くなる要件がそろっていくと考えています。また、業績連動型の株式報酬を導入できていないことも課題と認識しています。業績連動型の株式報酬は世の中のスタンダードであるので、グローバル企業として導入は避けて通れないと考えています。
澤田:株式報酬については、一般社員レベルでも重要だと考えています。従業員持株会では自動引き落としで株式を購入するので、株式の資産額をしっかりとは認識しないものです。株式報酬が付与されると、株価や資産額を気にするようになり、会社の戦略や業績、資本市場から会社がどのように見えているのか、社員も考えるようになります。その結果、目の前の業務に追われるような働き方ではなく、企業価値につながる仕事が何であるのか考え、働き方が大きく変わると考えています。
重富:業績連動型の株式報酬の目的は大きく二つあり、一つは長期的に利益を引き上げて株価上昇への強いインセンティブを持ってもらうことです。もう一つは、現金の代わりに株式が付与されるので、「株価を下げるわけにはいかない」という心理的な抵抗感や経営に対する責任感を持ってもらうことです。経営陣や幹部のみならず、一般社員にも株式報酬というインセンティブは有効だと考えています。会社全体で株主・投資家の皆様と同じ船に乗り、同一のベクトル上で事業運営することが重要です。
澤田:パナソニックホールディングスが真に日本を代表する企業となるために、これまでの在り様を一新していきたいと思います。5年後、10年後に随分変わったと言われるように、取締役会議長として努力してまいります。

◆パナソニックグループのオウンドコミュニケーションメディア Panasonic Stories
自らの言葉で思いを伝える/『ひと』を通じてパナソニックグループの姿を届ける。
グループの考え方や取り組み、挑戦をタイムリーかつ分かりやすくお伝えします。
※今回の取り組みはこちらでも紹介しています
URL https://news.panasonic.com/jp/stories/17760
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
